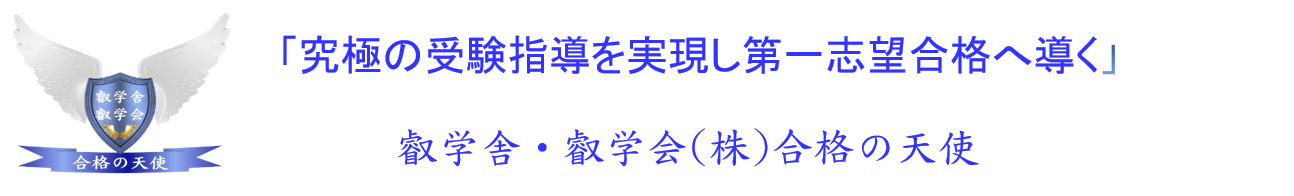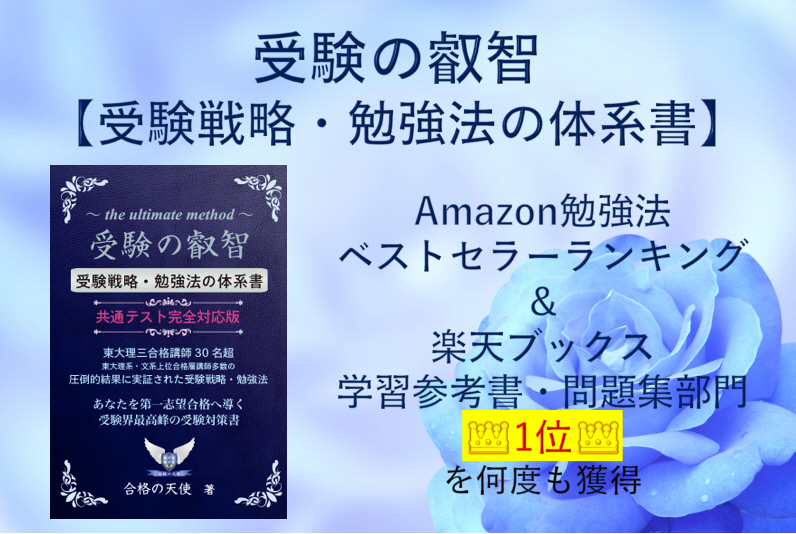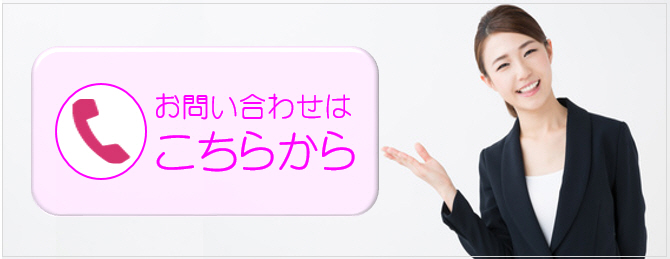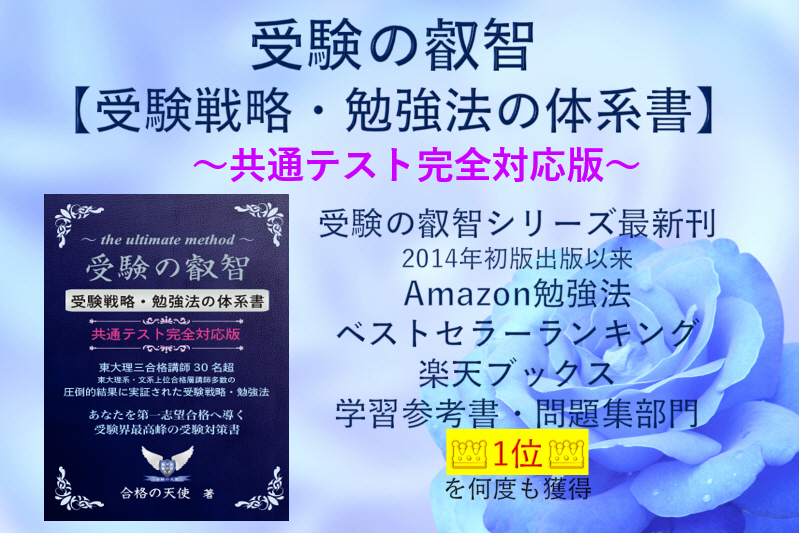数学の勉強法を具体的かつ実践的に学ぶ
数学を得意科目にしたい、さらに上のレベルに押し上げたい受験生の皆さんのために、 数学を極めた東大理三合格・東大医学部講師を30名超擁する 叡学会(株)合格の天使が贈る本当に数学を得意科目にするための方法、 数学の問題集・参考書への取り組み方や復習法について解説した動画です。
数学の勉強法は様々語られますが的を射ていないものがほとんどです。 また論理を前提とした具体的で実践的な数学勉強法というのはほとんど存在していません。 この原因は実際に受験数学を極めたわけではないのに数学の勉強法を語る人が多いからです。
このコンテンツでは、このコンテンツをご覧いただいたみなさんだけが得をする数学の勉強法動画をプレゼントします。いずれも受験数学を極めた東大理三合格=東大医学部講師の動画です。他では得られない核心を突いた数学の勉強法を学んで苦手科目を得意科目に、得意科目を武器科目に変えてください!
『コンテンツ目次』
1. 受験数学の到達点を勘違いしていると本物の実力はつかない
2. 数学の問題集・参考書の独学での正しい使い方とよくない勉強法
数学についての誤解をまず排除せよ
受験数学については様々な誤解がなされています。この数学に対する誤解を排除しないと先入観や思い込みで的確な対策が取れなくなったリ、結果が伴っていない数学勉強法に踊らされたりしてしまいます。このコンテンツをご覧いただいている皆さんはまず数学に対する誤解をきれいさっぱり取り除いてください。これが素直に数学の実力が伸びていくための秘策でもあります。
受験数学の到達点を勘違いしていると本物の実力はつかない
動画を見る前に以下の事柄にしっかり目を通してください。 数学の実力が伸びない勉強の方向というものがあります。 例年春先に毎日何人もの受講希望者の面談を行っているのですが、ここで多くの受験生がある共通の勘違いをしていることに気づかされます。
受験数学の到達点の勘違い
みなさんは当塾の東大理三合格講師陣が入試レベルの数学の初見の問題をどのように解いていると思いますか?
多くの受験生や保護者さんは東大理三合格者なんだから問題を見た瞬間、解法や答えまでの流れが一瞬で思い付き解答を導けると思っていると思います。
しかし、それは大きな誤解であり勘違いです。
もちろんそういう問題もありますが、骨のある入試レベルの数学はそんなに甘くはありません。しかもひらめきで解けるなどということはないのです。
あくまで蓄積した定石をもとに思考をこねくり回して手を動かしていくつかのパターンを試し試行錯誤しながら解答を導いているのです。
勘違いを生んでしまう原因は、解法の定石を蓄積する段階の話と初見の入試問題を解く段階の話を混同してしまっている、混同させられてしまっているということです。
試験本番の数学の入試問題を見た瞬間に解法が思いつかなければならないと勘違いしてしまうと、世の中の受験数学の問題はできるだけ解いておいた方がいい・もっと優れた問題集があるのではないか、予備校や塾のテキストでしか得られない問題があるのではないか、と誤解し追い求めてしまうのです。
思い当たる節のある方いらっしゃいませんか。
定石をストックする段階(標準レベルの問題集をマスターする段階)では最終的に問題を見たらポイントを踏まえたうえで解答までの過程をすぐに引き出せるレベルまでマスターする必要があります。しかしそのことと入試レベルの初見の問題をその次元で解くこととは別なのです。
あくまで定石をストックする段階(標準レベルの問題集をマスターする段階)というのは入試問題を解くための武器・道具を手に入れる段階です。だから一定(標準問題集1冊)の道具・武器をすぐに引き出せるように整理してストックしておく必要があるのです。
しかし、入試問題はその道具・武器を如何に使いこなせるか、例えば様々な種類の刃物(道具)を見たことない形をした対象物(入試問題)に応じて適切に選択して対象物をしっかり制限時間内に切ることが出来るか、ということが問われているのです。
この部分に誤解や勘違いがあると勉強の方向性が全く合格からズレてしまうのです。この部分の誤解や勘違いにはさらに2つのパターン分岐があるのですが、このお話はまたの機会にします。 第一志望合格へ向かっていきましょう。
数学は暗記科目?理解数学のすすめ!
数学の勉強法のそもそもの根本を東大理三合格講師が解説した動画です。数学を得意科目にするためには、そもそも数学の勉強法をどのようにとらえるか、そしてそれを日々の勉強や問題演習にどう生かしていくかが重要になります。
ここではこのそもそもの根本原理に当たる数学の勉強法について東大理三「次席」合格講師小団扇が解説します。数学を得意科目にしたい、数学に苦手意識がある、数学の勉強をしても成績が伸びないという皆さんは必見です。
理解数学のすすめ
数学は暗記かという点について間違った捉え方をしてしまうとどんなに勉強しても数学の実力はつきません。数学ってどういうものなのという観点からもこの動画を見てみてください。 受験数学を極めた東大理三合格者の数学のそもそもの捉え方を学んで数学を得意科目にしていきましょう。
暗記数学・理解数学について東大理三「次席」合格講師小団扇が解説
数学問題集・参考書・過去問集の優れた勉強法と使い方
数学の実力がしっかりとつくか否かは日々の数学の勉強法、問題集・参考書の使い方によります。どのように日々数学の問題に取り組むかで実力を確実にあげるために必須となるものが得られるかが決まるのです。単に問題演習を繰り返しても数学の実力などつきません。数学実力はセンスではなく日々の勉強への取り組み方ですべてが決まるのです。以下の動画から優れた勉強法を学んでください。
数学の基礎・標準問題集及び過去問集それぞれの勉強法
まずは数学の基礎・標準問題集及び過去問集のそれぞれの学び方の全体像を解説した動画をご覧ください。
数学の勉強法としてどの問題集・参考書も何度も繰り返す的な勉強法が語られますが、これは問題集のレベルに応じた役割を理解していない勉強法です。このような勉強法を実践していても目的がずれてしまい得るべきものを得られません。すなわち、実力は効率的に伸びません。
今回はこの点について地方公立高校⇒東大理三現役合格講師正門が解説した動画をプレゼントします。
今回の動画の内容は当塾の著書、
受験の叡智【受験戦略・勉強法の体系書】 ▶
医学部受験の叡智【受験戦略・勉強法の体系書】▶
に詳しく記載してあります。
この動画をご覧いただいた後、再度読み直してください。 本当の意味を理解していただけると思います。 これによりあなたの日々の勉強は効率化するとともに実力が伸びます! 必ず読み直して復習してくださいね。
数学の基礎・標準問題集及び過去問集のそれぞれの学び方を東大理三合格講師正門が解説
数学の問題集・参考書の独学での正しい使い方とよくない勉強法
東大理三合格者であれば問題集や参考書は最初からスラスラわかりものにしていけるのだと誤解されている方も多いと思います。しかし実際には最初からスラスラ解け、すべてを身に着けていけるなどということはありえないのです。
独学で数学の問題集や参考書を勉強していく際にどのように取り組んで行くべきなのか、実際に取り組んだのか、この知識と実践の差が効率の差です。
この点について当塾、東大理三合格講師 正門が皆さんのために動画を収録してくれました。 この正門は地方の公立高校から東大理三に現役合格している講師です。 是非、参考にしてください。
数学の独学での問題集参考書の使い方を東大理三合格講師正門が解説
数学の実力を伸ばす問題集・過去問集の使い方
問題集や過去問集に取り組む際に注意してほしいことがあります。 この部分わかっている人はわかっているのですが、多くの受験生が戸惑ったり、挫折してしまう原因になる部分ですのでチェックしてください。
皆さんはできなかった問題やわからなかった問題について解答・解説を読む際に何に着目していますか?
数学の問題集や過去問集の解答というのは「論理的に思考を構築した最終型」です。これは何となく理解している方も多いと思います。さて、では、実際に問題を解く際や解答・解説を読む際に留意すべきこの事実から導き出されることは何でしょうか?
みなさんがちゃんと問題集や過去問集を有意義に使えているならこの結論はすぐ出るはずです。
答えです。
上記事実から導かれることは、実際に問題を解く際の思考の順番や思考過程は解答の順番通りではない場合が多々ある、ということです。問題を見てすぐに解答の順番通りに問題を解くことなど出来ないということです。
むしろそのように解答を捉えてしまうならその問題から得るべきものを得ることはできません。また、この部分をわかっていないと問題集や過去問集をやっても結局それは解答を丸暗記をしているに過ぎないことになるのです。
おそらくここまでの話で色々に気づいてくださった方は多いと思います。以上の話の意味しっかり考えて問題集や過去問集に取り組んでいってください。これは結局初見の問題や応用問題に対処できるか、という話にもつながっていく部分です。
ですので問題集や過去問集の解答そのものをたとえお経のように唱えられるように繰り返したところで、初見の問題や応用問題に対処できる実力など全くついていかないのです。
今回はあえて考えていただくためにここまでにしますが、当塾の受講生の方は各自が使っている問題集や過去問集のできなかった問題・わからない問題の個別指導の質問回答のなかで常にこの部分の本当の意味について東大理三合格講師陣などから吸収していっていただいているので実力が伸びていくのです。 (以上に加え個別指導受講生に提供する受験戦略・勉強法講義でも適宜こういった話をご提供しますが、その一部をこのページをご覧いただいている皆さんにも無料提供しています。)
数学の問題集・参考書はレベルごとに目的が違う=使い方も違う
問題集・参考書はレベルごとに「仕様」も「使用」の目的も異なります。 したがって当然ですが「使い方」も異なるのです。
しかしながら一般的にはここの区別なしに勉強法や方法が語られています。 この区別を意識できていないと今やっている問題集・参考書から得るべきものを得られません。 鍛えるべき力を鍛えられません。
今回は受講生に毎週配信している受験戦略・勉強法講義の一部を特別に受講生以外のみなさんにも特別公開します。
今回の動画は一応数学をテーマに話していますが、このお話は全ての教科に共通する部分が多々ありますので数学が受験に必要がないという方も是非ご覧ください。
■東大理三「次席」合格講師 小団扇
■東大理三合格講師 荻原
の特別共演の動画です。
同じ問題集や参考書をやってもなぜ受験結果が異なるのか、という部分にも関連する内容ですのでこの観点も意識してみてみてください。
東大理三「次席」合格講師小団扇&荻原の動画
日々の勉強は継続的にこなす必要はあります。 ただし、問題集や参考書に見境なくなんでもかんでも回数をこなせばいいという勉強法では実力は効率的についていきません。
この動画の続きも想像しながら日々の勉強で得るべきものを目的に応じてしっかり得ていってください。 着実に第一志望合格へ向かっていきましょう。
数学の実力を確実にあげる問題演習法
東大理三合格者が数学の問題演習のやり方について解説した動画です。
動画を見て気づいてほしいこと
以上の動画の内容は、数学の問題演習を行う過程の一部にすぎません。
しかし、この観点で問題演習をしているかどうかだけでも、
・その問題を整理して理解できるか
・形を変えて問題が出てきたときにどこが違うのかに気づけるか
・他の問題にこの問題を活かしていけるか
・復習する際に効率的に行えるか(頭の整理の問題)
・その後演習する類似の他の問題と関連づけていけるか
これらに大きく影響してきます。
まだまだこの効用はあるのですが、それは以下の動画内容を実践して各自威力を実感してください。
地方公立高校⇒東大理三現役合格講師正門が数学の問題演習を解説
数学の実力差を分けるもの
先ほども触れましたが、今回の動画の内容は、数学の問題演習を行う過程の一部にすぎません。 問題演習を行う際のチェックポイントは他にもいくつかあります。復習方法も含めればさらにポイントは増えます。
大事なことは、こういったちょっとしたコツや実践方法の差が、数学の実力差につながっているということです。
当塾の受講生はこういった点も含め、数学に限らず、全教科について、最も優れたものを有している東大理三合格講師陣からすべてを手に入れることが出来ますが、みなさんもひとつづつ実践していってみてください。どの教科であっても、得意科目にすることが可能になります。 しっかり実践して、それぞれの第一志望合格に向かっていきましょう!
数学の実力を確実につける復習法
数学の問題演習をやっていると誰もが一度解いた問題をどのタイミングでいつ解きなおせばいいのか、どう復習すればいいのかという悩みに突き当たります。この部分について解説した動画を以下掲載します。
数学の問題を解きなおす理想的な時期
数学問題集の演習をしていると、どのタイミングで復習すればいいのか、どのくらいの期間で解きなおすのが効果的なのかを悩む方は多いと思います。今回はこの点についての解説動画です。
東大理三合格講師深川が数学の問題の解きなおし時期を解説
全く出来なかった数学の問題の復習法
数学の解法をマスターするためにはどうすればいいのか、というご質問をいただきましたので今回はそれに関する動画をアップします。
今回の動画は昨年度受講生に配信した動画の一部になります。こんな動画を毎週見ているのが当塾受講生です。しかも一部ではなくフル完結で。みなさんにも一部ですが今後もおすそ分けしていきますので是非参考にしてください。
数学の復習法を東大理三合格講師深川が解説
数学を得意科目にする思考法
標準問題集はしっかりやったのに初見の問題に対処できないという受験生は非常に多くいます。勉強したのに数学が出来るようにならない受験生というのは問題への取り組み方、思考に問題があるのです。ではどうすれば初見の問題に対処できるようになるのか、その方法について以下の動画を参考にしてください。
数学の問題演習のアルゴリズム化
数学を得意科目にする方法=問題演習をアルゴリズム化せよ←これが数学を得意科目にする極意の一部です。
どんなに時間をかけて勉強しても、どんなに多くの問題を解いても、どんなに優れた問題集を何回解いても実力が伸びない人は伸びません。 これはなぜでしょうか?
これには明確な原因があるのですが、それをわかりやすく端的に言ってしまうと、本当にできる人の思考や取り組み方で問題を解いてない、復習出来ていないからです。問題を解いて復習して何を得ていくべきか、という問題演習の実践の過程が実力が伸びる人と伸びない人では大きく異なるのです。今回はこの点についてお伝えします。
「問題演習をアルゴリズム化せよ」とありますが、これは当塾の著書、
受験の叡智【受験戦略・勉強法の体系書】 ▶
医学部受験の叡智【受験戦略・勉強法の体系書】▶
に記載している、問題演習の際の「一般法則化・普遍原理化・処理公式化」と同義です。
ですのでこの動画を見たら、今一度上記の当塾著書の該当部分を読み返してください。 しっかりこの部分を理解していけば、それだけで日々の問題演習が実力アップに無駄なく効率的につながっていきます。 大きく実力を伸ばす事が可能となり、他の受験生に大きく差をつけることが可能ですので是非、この部分の当塾の理論の理解と実践をしていってくださいね。
東大理三合格講師 正門が解説
正門は何度か当塾のYouTube動画に登場していますが、この正門は、東大理三合格者など開校以来出したことがない北海道の公立高校から理三に現役合格している講師です。さらに予備校にはいかずに自学自習メインで合格を勝ち取っています。
的確な勉強法を知りそれをしっかり理解し実践していけば、受験数学はもちろん他の教科もガンガン実力を伸ばす事が可能なのです。 是非この動画を参考にしてみてください。
なお、この動画も当塾のネット塾・リアル塾受講生に毎週毎週配信している受験戦略・勉強法講義の一部の受講生以外の皆さんへの無料提供です是非役立ててください。
典型問題を初見の問題に結びつける東大理三合格者の頭の使い方
前項で数学の問題演習のアルゴリズム化というお話をしました。 今回はその続編のお話です。
今回は、実際に東大理三合格者が典型問題と初見の問題をどのように結びつけているのかの「頭の中」のお話です。本来無料公開するものではないですが、一部だけ無料公開します。
東大理三合格講師 正門&荻原が解説
なお、この動画も当塾のネット塾・リアル塾受講生に毎週毎週配信している受験戦略・勉強法講義の一部の受講生以外の皆さんへの無料提供です是非役立ててください。
本当に優れた数学の勉強法、医学部・難関大学(理系・文系)の数学で高得点を獲得する勉強法をお友達やお知り合いにも教えてあげてください。以下のシェアボタンを押せば簡単にシェアできます。