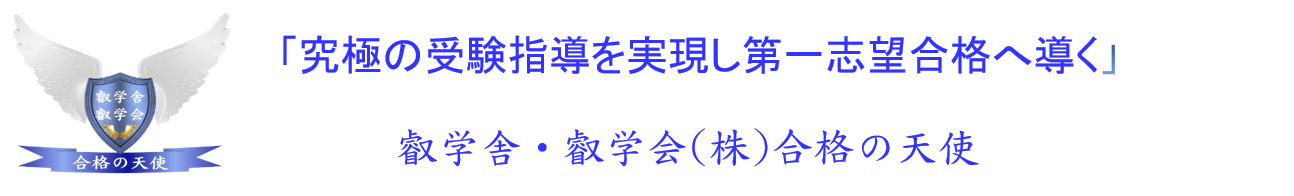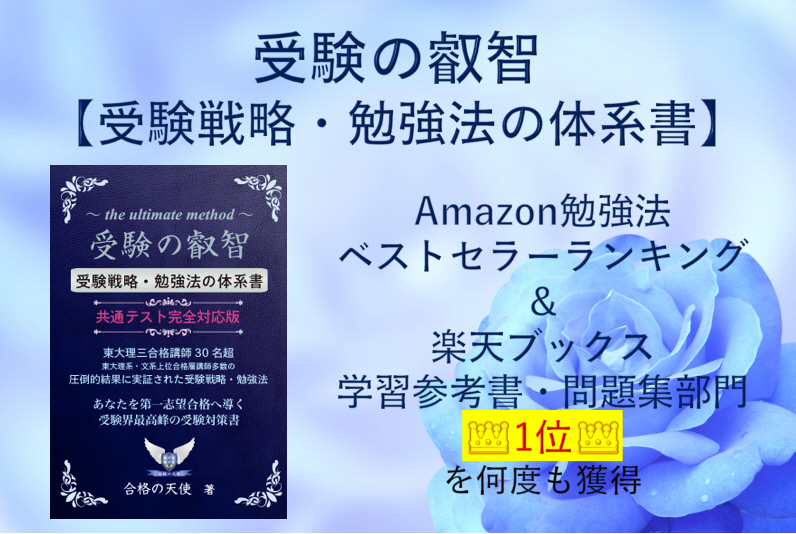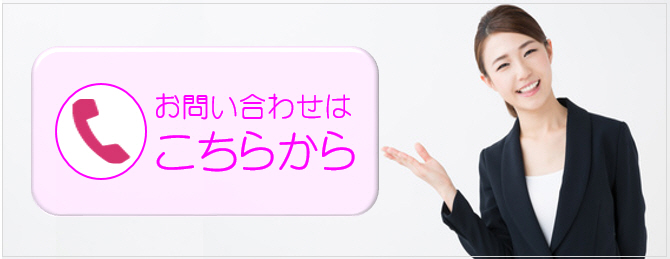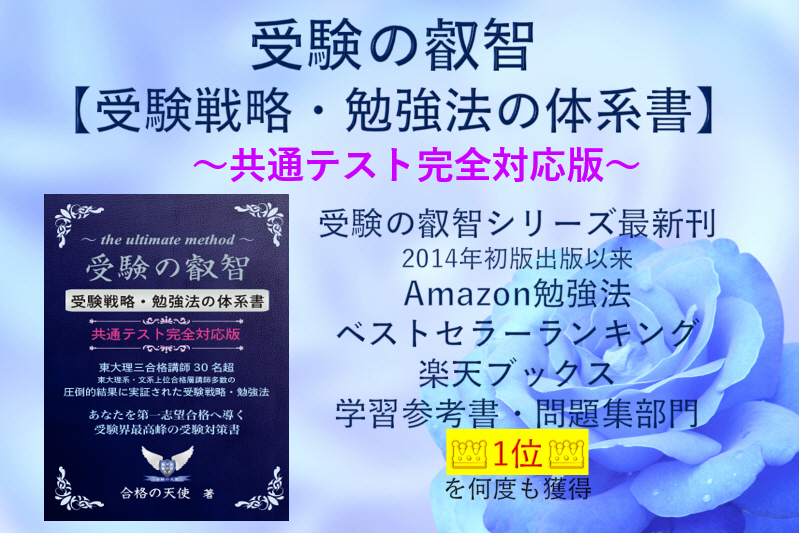結果に実証された的確な生物勉強法を手にしてください
生物の勉強法と対策のコンテンツでは当塾が誇る 東大理三合格、東大理二「首席」合格(東大医学部医学科)講師 による合格するための生物の勉強法と対策をお伝えして行きます。
いきなりチェックポイント!
当社(株)合格の天使の著書やコンテンツは、 以下の点で他の勉強法本や勉強法サイトと大きくその有用性・的確性・信頼性が異なります。
■生物で圧倒的実力をつけたからこそ東大理三合格、東大理二首席合格している講師陣が提供している内容である事
■実際に上記講師自身が受験科目として生物を受験し実証・検証している内容であるという事
⇒これが的確かつ優れた勉強法を導ける絶対的条件であり当社コンテンツの優位性です。
世の中には、参考文献・サイトを示さず
・自身が受験生時代に勉強もしていないのに生物の勉強法を語るもの
・二次試験・個別試験物理で高得点を取っていない人がそれをとる方法を語るもの
があります。
しかし、自身が勉強も受験もしていない科目や自身が本番で実際に高得点を獲得していないのに
高得点を取る方法を語るとするならばそれは
・本質を突いたものでない
・確実に実力を伸ばす方法ではない(得意科目にまでは出来ない方法)
・間違った勉強法である
・他からの無断拝借・剽窃である
のどれかもしくはその全部に当てはまると言えます。
みなさんは、圧倒的結果に実証された生物の勉強法を このコンテンツからしっかり学び全国の受験生に対して 大きなアドバンテージを得て生物を確実に得意科目にしてください!
なおこのコンテンツの内容の一部は、当塾著書、
「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】
「医学部受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】
の記載内容を含みます(厳重な著作権保護対象です)
上記著書と併せてご覧いただくことで確実に実力を伸ばす化学の勉強法を学んでいただけます。
※このコンテンツ内でご紹介している問題集・参考書のリンクについては古いものもございますので、 もしご購入される場合は新しい版のものをご購入ください。
<高校生、受験生及び保護者の皆様へのお願い>
近時、当社(株)合格の天使の著書「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】、「医学部受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】及び公式サイトのコンテンツから同業者・指導者が当社コンテンツを用いて自己のコンテンツとして自身のサイトやSNSで無断使用していることが確認されています。このような倫理観や法令遵守意識が欠落した行為は許されるべきではなく、そのような実力仮装行為に惑わされる高校生や受験生にとっては害悪以外の何物でもありません。このような行為、コンテンツを発見した際には当社(株)合格の天使までお知らせください。同業者・指導者による無断使用・転載・転用及び出典や参考文献を示さない行為には厳粛に対処させていただきます。
まずは動画で!東大理三合格者が化学を得意科目にした勉強法
まずは当塾東大理三合格講師前田の動画をご覧ください。 前田は理三無名校から理三合格を成し遂げた経歴をもちます。 是非参考にしてください。
生物の性質から導かれる勉強法の注意点
生物の科目特性から見る勉強法の注意点として以下2つのポイントに着目してください。
数学が苦手だから生物を選択するという考えは安易すぎる
世の中では、数学が苦手だから生物選択という教えや流れが一般的ですが、実験考察問題が課される難関大学については受験生物と数学にはある意味同じ特徴があると当塾は分析しています。それは、標準問題集と試験問題の乖離が大きい科目という点です。
数学は、この部分を埋めるノウハウはそれなりに世の中にはあります。(とはいえ、的確なものはごくごく一部ですが)これに対し、生物に関してはこの部分の優れたノウハウは受験界にはほぼ存在しません。
当塾の東大首席合格講師や東大理三合格講師もこの部分は自分でノウハウを集積して来たという事実があります。世の中の指導にも参考書にもこの部分についてきっちり書かれた優れたものは存在しなかったということです。
この部分について、当塾は東大首席合格講師や東大理三合格講師のノウハウを集積し体系化して保有しているのです。ですので、生物選択の受講生にも的確な指導を行うことが可能であり、医学部はじめ難関大学に生物選択でも合格者を輩出できるのです。
生物の優れたノウハウがなぜ受験界に存在しないのかについては明確な理由があります。みなさんは東大理系合格者の理科の選択科目の偏りをご存知でしょうか。東大理一合格者で生物選択者はほとんどいません。東大理三合格者の生物選択者も非常に少ないです。東大理二合格者になると多少生物選択が増えるという程度にすぎません。この事実から受験生物を本当の意味でマスターしている人間はごく限られた数しか存在しないからなのです。
生物の試験問題の客観的性質として得点しにくいわけではない
上記で、現状の受験界の状況についてご説明しましたが、このことは、生物の的確な対策が難しいということを意味するにすぎず、生物の試験問題の客観的性質として得点しにくい問題が出題されているわけではないということを意味するのです。この部分は世の中の受験指導では明確にされることがない部分ですので、このコンテンツをご覧いただいている皆さんは希望を持ってください。
以下では、具体的な生物の勉強法と対策について触れていきます。
生物をマスターする勉強法のポイント
まず、大学受験生物を高い次元でマスターするために、生物の試験問題の特徴や何をいつまでにやればいいのか、さらには実際に出題される問題の種類ごとの対策のポイントを解説していきます。
大学受験の実際の出題から見た生物の勉強法と対策の核
大学受験の生物の問題は、生物の幅広い分野から出題されている場合や多くの分野を融合させた融合問題もある場合があるが、まずは教科書レベルの知識をまず確実に習得することが最優先順位。
難関大学の生物問題の大きな特徴は教科書に記載のない実験考察問題が出題されるということである。実験考察問題は誰も知らないような高校範囲外の題材が使われる。または知っている題材でも別の角度から実験を設定してくる場合が多い。問題集にはないオリジナルの問題が多いのである。
しかし知識として求められているのはあくまで教科書レベルの知識であるということを誤解してはいけない。それ以上の知識を必要として解答を要求しているわけではない。この点を勘違いするといくら努力しても点は伸びない
実験考察問題は条件設定が丁寧であり、リード文や、高度な知識、用語には注釈が付いている。リード文やデータ等の与えられた資料をしっかり読めば基礎知識をもとにとけるように解答のヒントがその中に含まれているのである。
解答のヒントを見つけ基礎標準知識から如何にデータ等を読み取り、つなぎ合わせ論理的に推論し解答を導けるかが試されているに過ぎない。過去問演習をしっかりとやって思考の訓練をしておけば充分に得点でき差をつけやすい問題なのである。
このような出題のある大学は、単に知識を暗記しているだけで思考のできない受験生は要らないという意思表示でもある。 過去問演習を通じて解説、模範解答を見て、要求されているポイント、思考方法、解答の仕方、頭の使い方、知識を再確認していくことで必ず対処できるようになる。
基本方針&年間計画の概要
教科書、傍用問題集(セミナー生物等)で基礎を徹底的に習得し、知識型論述の問題集・参考書で記述・論述のパターンや作法を一通り学んだらできるだけ早い段階で志望校の過去問演習に入り志望校の『過去問基準で基礎標準知識をとらえなおし』 (「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】のキーワード。著作権保護・要引用明記)ブラッシュアップして行く+基礎知識の習得⇔共通テスト過去問演習の往復で共通テスト対策とともに基礎知識盤石にしていくという方針をおすすめする。 (この点の詳細は著書「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】を是非ご覧ください。)
※生物の共通テスト対策と勉強法の詳細は 共通テスト生物の勉強法と対策をご覧ください。
ここでは「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】に掲載してあるフローチャートの一部を文字で抜き出してお伝えします。
【7月~9月】
教科書及び教科書傍用問題集(もしくは同一レベルの基礎的参考書・問題集)
基礎知識習得後⇒知識型論述問題集(セミナー生物の論述問題部分or「生物記述・論述問題の完全対策」等)
【9,10月~11月】
理系受験生:志望校の二次試験・私大の過去問(基礎の習得が遅れている場合10月終わりや11月にずれ込んでも問題ない)+知識確認のための共通テスト過去問
【12月】
共通テスト・志望校の二次試験・私大の過去問
【1月~共通テスト】
共通テスト過去問
【共通テスト後】
志望校の二次試験・私大過去問
※過去問演習に入った後は、志望校の過去問・共通テスト過去問⇔上記各問題集・参考書の『サイクル学習』『基礎標準知識を過去問基準でとらえなおす』『過去問至上主義』(「受験の叡智」から引用 著作権保護・無断使用禁止・要引用明記)を行っていく。詳細は著書「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】を熟読して下さい。
高校1,2年生の基本方針
闇雲な先取り学習は難関大学合格のためには必要ない!
生物の勉強法の基本方針&年間計画の概要で受験年の受験生向けのものをお伝えしているが、まずそれをご覧いただきたい。受験年の夏休みに生物を含め理科は徹底的にまとめて問題演習に入れれば受験対策としては盤石になる。ということは高校1,2年生の段階で焦って先取り学習をする必要はない。まず大事なことは高校1,2年生の勉強法のコンテンツの中でもお伝えしているが、英語、数学の基礎を固めることが難関大学合格のための勉強法としては最優先であるということである。
高校1,2年生の段階では生物への勉強法と対策としては履修年に授業の進度に併せて教科書や傍用問題集についてこのコンテンツの中でお伝えしている生物の勉強法の視点を意識してしっかり勉強しておくだけでどの大学にも通用するだけの盤石な受験対策となる。
この生物の勉強法と対策のコンテンツ、さらには著書「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】を熟読して本当に必要な大学受験の生物の勉強法や対策の核をきっちりと捉えてください。この部分だけ的確なものを得ておくだけでも大学受験の生物の勉強法と対策としてはものすごく大きなアドバンテージを得ています。
知識型記述・論述問題対策
記述・論述問題の勉強はしっかりポイントを押さえて行う!
大学受験の生物で高得点を獲得するためには教科書及び教科書傍用問題集(もしくは同一レベルの基礎的参考書・問題集)で生物の基礎知識を習得したら次に志望校の出題形式に応じて知識型の記述・論述問題への対策と考察型の記述・論述問題への対策が必要になる。大学によっては知識型の記述・論述問題問題しか出題されない大学もあるのでこの点は各自の志望校の過去問を必ず確認して対策を行うことが重要になる。
知識型の記述・論述問題しか出題されない場合は考察型の記述・論述対策は必要がなくなるので無駄なことをしないように注意が必要である。
知識型の短文論述は配点ポイントが限られていることに注意が必要である。配点ポイントとなるキーワード、キーフレーズは常に意識して知識の補充や記述対策の勉強を行っていただきたい。
知識型の記述・論述対策のおススメ問題集としてはセミナー生物の該当部分もしくは
生物記述・論述問題の完全対策 (駿台受験シリーズ)をあげておく。
大学入試生物で最も厄介な実験考察問題の勉強のポイント
実験考察問題対策は過去問演習をしっかり行おう!
大学受験で出題される実験考察問題を苦手とする受験生は多いが以下の視点を持って勉強に取り組もう。実験考察問題に取り組む際には、リード文の読み方(アンダーライン等のチェックを入れる、メモを取る等)も過去問演習を通じて訓練しておこう。時間が厳しい大学の生物(理科)の出題ではこういう地道な努力がものをいう。
難関大学の生物の実験考察問題はオリジナル問題であるから他の問題集・参考書では代用不可能である。過去問演習こそがもっとも効果のある勉強法である。
実験考察問題の解答は多くが1~3行程度の論述式である。問われていることがわかっていても表現できなければ得点にならない。ポイントをついた過不足のない表現ができるように過去問演習を通じて訓練すること。
本当にどの科目にもいえることだが、難関大学合格の難しさのひとつは解答形式が記述、論述式の問題に対してポイントをついた過不足の無い答案を時間内に作成することである。とにかく実際に書く訓練を怠らないことが必要である。
添削指導は必ず受けよう。生物の実験考察問題(数学や物理、化学も同じ)でどのような答案を書けば高得点を取れるのかを熟知しているのは実際に自身が難関大学の大学入試問題で高得点を獲得した人のみである事実も知っておくと安易に語られる勉強法や指導に惑わされなくて済む。
生物遺伝計算問題への対策
多くの生物選択受験生が苦手とする遺伝計算問題の効率的な勉強法!
「試験本番で得点しにくい」「医学部受験生のネックになっている」とも言われる生物ですが、生物選択でありながら東大理二「首席」合格という結果を出した大久保が受験生の苦手とする分野について基礎からわかりやすく解説しています。
受験生視点で、こういうものが欲しかった、こう考えればわかりやすい、ここのポイントを抑えておけば確実に理解・得点できるということを網羅的に取り上げた「生物遺伝計算問題特講」の一部を皆さんに無料提供します。 この「生物遺伝計算問題特講」は遺伝の計算問題を全15回に分けて講義し、5回の問題・添削、生物に関する勉強法の質問はなんでも可能な単科の講座です。
的確にポイントをつかみにくい、的確な指導を得難い生物について、東大理二首席合格、慶応大学医学部合格、早稲田大学先進理工学部特待合格という結果を出している大久保から多くのものを得てください。 質の高いノウハウやエッセンスを網羅的に得ることが出来れば生物も必ず得点源にできます。
時間対策も考慮した上での大学受験生物のへ対策
難関大学合格のためには時間不足への対策を考慮した勉強を行っていくことが重要!
理科2科目が課される大学の場合化学・生物選択者は時間がかなり厳しいので得意な科目のほうからやるのが一般的。これに従う必要はないが過去問演習、模試等で解く順番、時間配分を各自決めておくということが大切。そして本番では状況に応じて臨機応変に対応することが必要。 はじめに目をとおして得意分野やすぐに解けそうな問題があったならその順番にこだわる必要はない。
生物を含め理科は大学入試本番ではとにかく時間との勝負である。解ける問題からどんどん処理していく、解答に詰まったら頭をクリアーにする意識を持ってどんどん次の問題へ進むこと。とにかく解ける問題を可能な限り多く解ききるという意識を持って本番に臨むことが重要である。そして終盤になってもあせらず淡々と時間のある限り目の前の手をつけている問題を処理していくことが重要である。
多くの東大合格者も東大理科をすべて解ききってはいないのである。数問残しても問題ない。解ける問題を確実にとき、ケアレスミスも最小限に抑えれば合格点には充分届く。 この事実をしっかりと踏まえたうえで日々の生物の勉強や過去問演習に励むことで実力の伸びも結果も大きく異なる。
生物で高得点を獲得するための具体的な勉強法と手順
以上みてきたように、生物を高い次元でマスターするには様々なポイントがあります。これらのポイントに留意するとともに、以下の生物の勉強法、勉強の手順を踏んでいくことが重要です。 ここでは都立トップ高校「首席」合格⇒東大理二合格講師山本の書下ろし記事を掲載します。
基礎知識の習得
まずはエピソードレベルの理解!
こんにちは、講師の山本です。
今回は基本的な生物の勉強法について書かせていただきます。
初めて触れる範囲を進めていくときについての話となります。
実際の勉強の流れとしては、 勉強する範囲(例えば教科書第一編第3章代謝とエネルギーの呼吸を勉強するという時)について教科書のその範囲をとりあえず内容を理解するスタンスで読みます。 その後もう何回か全体の構成も意識して読みます。(小見出しなどを書き出したりして)
そうしてこの範囲はこういう内容が並んでいて、この話は要はこういう話なんだなという風に自分の中でまとめます。 表現が難しいですが、まとめノートを作るといったことではなく、一つ一つの内容に対して知っているという感覚を持つというようなことであったり、長い説明についてもパッと見てどういう話がされているか大体分かるといったような感じです。
この段階ではあくまでもエピソードレベル(?の)理解であって、用語などはまだちゃんとおぼえていないと思います。しかも、勿論すべて完璧なわけはなく、次セミナーを解く時に実際には分かってなかったものもあったりします。 用語は高校で配布された一問一答のプリントで覚えた気がしていますが、一問一答問題集でも同じことが出来ると思います。
次にセミナー生物を解きますが、一応章の最初にあるその範囲の説明もざっと読みます。後は解きながら気になったところをその都度教科書や図説を参照して、自分の認識が教科書やセミナーの内容と辻褄が合うようにしていきます。
知識論述対策
インプットとアウトプットの視点!
今回は知識論述について書かせて頂きます。
生物という科目において知識論述は一つのテーマかと思います。進め方としては、知識論述問題集などで、まずインプットをしていきます。 インプットは、文それ自体を覚えていくのではなく、何の要素を書くのかというのを覚えてアウトプット出来るようにします。 エピソードとして、これについて説明をする時はこれとこれとこの話だよな、ということが思い出せるといった具合です。
知識論述の勉強は、生物学的意義など様々な話を吸収出来るので、まずはこういった観点で勉強すると良いと思われます。 その上で実際に書く段階は、問題演習で養っていく面と、典型的な論述に関しては、何回か書いて覚えてしまうという面があります。
実験考察問題、考察論述対策
演習の目的!
今回は二次試験型問題の演習の進め方について書かせて頂きます。 ここで二次試験型問題とは、何か題材を基に知識論述やデータの読み取り、考察などをさせるような国公立二次試験、私大の過去問などを指しています。
まず計画としては、分野ごとに区切りこの期間でこの分野をやるという形が復習の面でも良いと思います。
問題を解く演習の目的ですが、個人的には
●第一に典型的な題材についてデータの読み方を理解すること(目の付け所、こういう風に解釈が出来ますよねというのを理解する)
●第二に考察を含めた論述の書き方を身につける(何を書けばいいかまず要素レベルで考えてから、論述答案にする流れ)
といったところにあると思います。
やはり基本的な知識を持っているといえど、初見でデータを上手く素早く解釈していくのは難しいので(出来ないとは言いませんが)、 読み取り方や書き方を経験し、さらに典型的なパターンに関しては既知の状態であることは生物という科目においてもある程度必要なことだと思います。
問題演習の目的は以上のものですが、実験考察問題については読解のコツや復習の仕方が非常に重要です。これが生物高得点への肝となる部分です。 この点についてはまたの機会に掲載します。
生物のレベル別問題集・参考書と勉強法
問題集や参考書を何を使うか悩む方は多いと思いますが、
定評がある問題集や参考書であれば学校で配られるものや現在使っているもので問題はありません。
注意すべきなのは、
■基礎からしっかりと段階を踏むこと
■自分の現在の実力にあったものを使う事
■問題集や参考書それぞれの目的に合致した力をつけるために、目的意識をはっきり持つこと
です。
以上がしっかりしていればあとは何を使うかではなく、何をどう得ていくかが大事です。
基礎レベルの問題集・参考書と勉強法
生物の基礎をマスターするには教科書を読み、該当範囲を基礎的な問題集でアウトプットしていくことが最もおすすめです。
生物は記述・論述問題が志望校の問題で出題されるとしても、まずは基礎知識がないと始まりません。また生物は他の理科科目に比して覚えることも多いです。したがって、この基礎レベルの問題集でまずは徹底的に基礎知識を習得しましょう。
以下おすすめの問題集をあげます。
『セミナー生物・生物基礎』
学校でセミナーが配られた場合はこれをマスターしましょう。最初は入試レベルのの問題部分はパスして基礎部分だけを習得する方法もお勧めです。
学校で配布される物であるため、解答冊子をもらえないことがあるかと思いますが、解答冊子をもらって勉強を進めるのが効率的です。解答冊子をもらえない場合は以下のエクセル生物を基礎問題集に据えて自分で使用していくのもありです。
『エクセル生物』
セミナー生物を持っていない人はこちらがオススメ。問題演習はすぐに回答を確認できないと効果が半減してしまうので、解答もついていて書店でも買えるこちらはおすすめです。図がきれいで解説も丁寧という特徴もあります。
標準レベルの問題集と勉強法
生物の標準レベルの問題集は知識、思考をより入試レベルに適合させていくものになります。
『基礎問題精講』
各単元必修問題、実戦問題に分かれており、章末に演習問題という構成となっています。必修、実戦問題はセミナーの例題のように問題と同じページの見開きに解答解説がついている形態です。
全体的に考察問題は演習問題 の一部のみで、残りは知識問題といった感じです。内容的に基礎的問題集として挙げた傍用問題集と重複が多いです。解説は豊富で丁寧であり、分かりやすいです。
志望校の問題の難易度によって、先に上げた基礎問題集1冊をマスターすれば十分という大学も多いです。また、標準レベルの問題集を使うとしても、この基礎問題精講レベルで十分という受験生も多いので闇雲にレベルの高い問題集を使わないように注意してください。
一応の目安として、実験考察論述が課されない地方国公立医学部や理系学部,私大理系学部であれば、この問題集までで十分と言えます。以下に掲載する「生物 標準問題精講」はレベルが高いのでむやみに使用する必要はありません。
この点は自分の志望校の生物の問題がどのくらいの難易度で、さらに問題の性質としてどのようなものなのかをあらかじめ受験生物できっちり得点を獲得している人に聞くのがベストです。
理系の生物を勉強していなかったり、まともに受験で得点を獲得していないのにいのに、生物の勉強法を語ったり、問題集や参考書を語る人の見解に踊らされないようにしてください。生物は特に高いレベルでマスターしている人が限られる科目です。くれぐれも注意してください。
『標準問題精講』
実験考察、計算問題が主であり、レベルは実験考察問題・論述が出題される旧帝大レベルの国公立二次、難関大対策に向いています。解説が非常に詳しく丁寧です。単科医科大などで出題される得点する必要のない問題を除いた問題の対策(=生物の対策)はこれで十分だと考えられる。こちらは 問題と解説で冊子が分かれています。
生物の論述問題に対処する問題集と勉強法
以下の良いと思った方を使用すると良いです。
『大森徹の生物 記述・論述問題の解法』
前半に一般的な構文(こういった論理的な構造はこのように表すと簡潔であるというような)について解説がされているのが良い点です。後半は標準的な知識論述問題と解説が並んでいます。
『生物 記述・論述問題の完全対策』
知識論述部分に関してはこちらの方が優れていると感じられる。この点についても志望校の問題によってどちらを使う方がいいのか受験生物できっちり得点を獲得している人に聞くのがベストです。
生物考察論述対策の問題集・参考書と勉強法
生物の考察論述の問題集は、思考力が要求される考察論述が出題される大学以外の受験生は使用する必要がないことに注意してください。
生物実験考察問題入門(駿台文庫)
実験考察論述問題の書き方が解説されている。あくまでこの参考書を使うのは知識型の記述論述問題集をマスターした後である事に注意していただきたい。
生物考える実験問題50選(駿台文庫)
これも実験考察論述対策の問題集。これも知識型の記述論述問題集をマスターした後に使用すること及びこのレベルの問題集があなたが志望している医学部の入試問題対策として本当に必要なのかは受験生物をマスターしている人にチェックしてもらってください。なお、「生物・新考える実験問題100選」についても同様です。
生物に興味をもつ勉強法
大学受験で生物の勉強をしていると、無味乾燥な勉強になりがちです。しかし、今やっている生物の勉強が大学の勉強にどのようにつながっていくのか、今、どのような現象の基礎を学んでいるのかを少しでもイメージできると、今までと違った見方で受験生物を見ることが出来ます。
ここでは、そのイメージを少しでも持っていただけるよう生物選択で東大理二に首席合格、その後東大内の進振りで東大医学部医学科に進学した当塾講師大久保が、みなさんへ書き下ろしてくれたコンテンツを掲載します。
はじめに
みなさんこんにちは。講師の大久保です。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが僕は高校時代の理科では生物化学を選択しました。物理も非常に面白く物理も捨てがたかったのですが、高校2年生の初めに分子生物学と遺伝子操作技術について習ってから、生命科学の面白さに惹かれ生物を選択しました。結局はそれが医学部に進むきっかけになった、という具合です。
大学生になって医学部に進学し、さらに詳しく生命科学(およびその応用である医学)を学ぶに連れて、自分が高校時代に生物を学んだ経験がものすごく生きていると感じたので、その経験を共有したいと思いこの記事を書いています。医学部を志す方は、今の勉強が将来にどう繋がるのかというイメージが少しでも浮かぶと幸いです。
あくまでも医学生が書いているということをご理解いただき、細かい点では実臨床に則さない部分もあるかもしれないことをお許しください(ホルモン名などは高校生物の教科書に即して書いています)。
フィードバック調整
さて、第一回は「ホルモン」の話をしたいと思います。高校では鉱質コルチコイド、糖質コルチコイド、甲状腺ホルモンなど様々なホルモンとその作用、および重要な概念としてその濃度維持機構としてのフィードバック調節について学ぶと思います。
当然、こうしたホルモンが出なくなったり、出過ぎたりすると体にも異常をきたします。すなわち、病気になるわけです。今皆さんが必死になって覚えているホルモン1つ1つについて、そのホルモンの異常による疾患が存在します。大きな病院に行くと「内分泌内科」「糖尿病・代謝内科」という科を見たことがあるかもしれませんが、これらの科はホルモンの異常による疾患の診断と治療を扱います(この他にも婦人科や泌尿器科などホルモンと密接な関係にある科があります)。
具体例
一つ例を挙げて見ましょう。 橋本病(Hashimoto thyroiditis)という病気が知られています。これは「甲状腺の機能が低下」する疾患です。本来は自分を攻撃しない免疫系が、なぜか自分の甲状腺を敵とみなして攻撃してしまうことによって甲状腺の機能が弱まってしまう病気です。
甲状腺から出るホルモンはチロキシン(甲状腺ホルモン)と習いましたね。甲状腺の機能が弱まるということはチロキシンが出にくくなってしまうということです。チロキシンの作用は、「全身の代謝を高める」と教科書にも記載されています。また、チロキシンの分泌調節系は
視床下部からの甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
→脳下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモン
→甲状腺からのチロキシン
となっており、チロキシンが視床下部や脳下垂体前葉に対して負のフィードバックをかけることで増えすぎることを防止していることも習ったと思います。
では、甲状腺の機能が低下してチロキシンが出なくなったらどうなってしまうでしょうか?
生物的に起こる現象
全身の代謝を高めるチロキシンが出ないことで代謝が下がってしまいます。よって、体重が増えたり、体温が下がったり、(汗の出る量が減ることで)皮膚が乾燥したり、(心臓の代謝が下がることで)脈が遅くなったりします。また、甲状腺が免疫系に攻撃されてしまうので甲状腺が腫れます(これはチロキシン不足とは関係ない症状です)。
こうした症状を呈する方が目の前に現れて、「この人は甲状腺機能低下症かもしれない」と思ったら、どうやって確認すれば良いでしょうか?ここで先ほどの負のフィードバックが生きます。
受験生物から考察
まず、血液検査をした時に血液中のチロキシンの濃度が低いことが予想されます(だからこそこうした症状で患者さんが困っているのです)。それに加えて、負のフィードバックの影響も考えなければいけません。
つまり、もし甲状腺がやられているために甲状腺からホルモンが出ないことが原因なのであれば、視床下部や下垂体は元気なはずです。その場合はチロキシンが低いことにより負のフィードバックがかかり、視床下部からの視床下部からの甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン、脳下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモンは増えるはずです。 逆に、もし下垂体の機能が低下していることで甲状腺刺激ホルモンが出なくなり、それが原因で甲状腺からチロキシンが出ないのだとしたら甲状腺刺激ホルモンとチロキシンがともに下がっているはずです。
以上のことは血液中のホルモン濃度を測ることで調べることが可能です。 つまり、この負のフィードバック機構をうまく使うことで、血液検査によってチロキシンが出ていないのがどの部位に原因があるためなのか、ということが大まかに推定できるのです。
橋本病では甲状腺自体の機能が低下しており基本的に視床下部や下垂体は元気なので、前者、チロキシンが下がりますが、甲状腺刺激ホルモンの濃度は上がっているという状況になるはずです。
もちろんこれだけで橋本病の診断ができるわけではなく、他にも色々な検査をして初めて診断がつきますが、高校の生物を習っているだけでもこの病気についてここまで理解できる、ということをわかっていただければ幸いです。
治療は、基本的に不足しているチロキシンを補うことになります。そうすることで全身の代謝をあげて症状を改善しよう、という戦略です。
高校生物の先に広がる世界
このように、高校生物で習う「負のフィードバック機構」や「ホルモンの機能」は、診断方法や症状、治療の理解へとつながっていきます。 もちろん大学から生物を始める人もホルモンについては大学で習うので心配しないでください。ただ、このような世界が高校生物の先に広がっているということを少しでも感じていただければ幸いです。
長くなりましたが初回は以上です。次もまた医学に関連した高校生物の話をしたいと思います。
難関大学合格をも可能とする究極の生物の勉強法と対策
世の中では大学受験の生物では高得点が取れないとか、とらなくてよいとかそういった話や指導があったりします。 しかし、医学部や理系受験生の大半は「物理・化学選択」か「化学・生物選択」であり、 そうである以上、生物選択者は大学受験においては物理選択者と得点を争わなければならないのです。
この現実を考えるなら大学受験生物で高得点をきっちりとるべき対策をしなければ医学部や難関大学の理系には合格できません。 的確な対策をとって第一志望合格を現実的なものにしましょう。
生物及び生物勉強法指導の現実を知ろう
難関大学合格という結果には的確な勉強法と対策が伴っています
生物の勉強法に限らず例えば過去問が重要であるということは言うまでもないですし誰でもそれだけなら語れます。
しかしあなたの志望校の問題をみてどの程度のレベルかがわからなくて的確な指導ができるでしょうか。
実際にどのような思考で解答すればいいのかがわからなくて的確な勉強法の指導ができるでしょうか。
あなたの日々利用する問題集について、あなたの自宅学習について、過去問という到達点のレベルを的確に把握できなくて、実際に解答できなくて、アドバイスできるでしょうか。
試験科目すべてに現在も精通していなくて、実際に解答できなくて、どの程度の労力を要するかがわかるでしょうか。 効率的なスケジューリングを導くことができるでしょうか。
あり得ないことは理論的に明確です。でも世の中ではこの部分が当たり前にごまかされているのです。
圧倒的結果に実証された実力を有する合格の天使講師陣から本当に有益なものを得てください。
本当に優れた対策で生物を得意科目まで押し上げる
実際の大学受験生物で高得点を獲得している講師陣による高次元の指導!
東大、旧帝大、国公立医学部医学科、早慶への驚異的合格率の秘密
合格の天使の指導の7大特質と3大ポイント ▶
ごく少数受講生ながら東大、旧帝大、国公立医学部医学科、早慶への驚異的合格率を誇る
合格実績と受講生及び保護者様の合格体験記 ▶
各科目勉強法、各自の合格計画の立案はもとより各自の使用する教材について科目・質問数・質問事項無制限指導を行う
WEB個別指導塾 ▶
対面講義と各科目勉強法、各自の合格計画の立案はもとより各自の使用する教材について科目・質問数・質問事項無制限指導を行う
リアル個別指導塾 ▶
生物について大学受験で高得点を獲得するために必要なエッセンスや核、思考方法について各分野・各項目すべてにわたって網羅的かつ体系的に得ることを可能とした
映像講義 ▶
医学部生物・共通テスト生物・生物基礎の勉強法
医学部受験生向けに別途生物の勉強法のコンテンツがあります。 また理系受験生の共通テスト生物の勉強法、文系受験生の共通テスト生物基礎の勉強法については 当然ですがこのコンテンツとは異なる対策が必要となります。 以下では、医学部受験生向けの生物の勉強法及び共通テスト生物と生物基礎の勉強法と対策についてのコンテンツをご案内します。 なお、医学部受験生向けの生物の勉強法はタイトルは医学部のものが入っていますが、 難関理系を目指す方も十分役立てていただけますので是非ご覧ください。
医学部受験生向けの生物勉強法コンテンツ
世の中には実際に受験科目として生物を勉強していないのみならず、医学部に合格していない、医学部に合格する生物の実力など全くないのに勉強法を語るものが沢山あります。このようなものが的を射た勉強法や対策でありはずはないことは本来自明です。
このコンテンツは、30名超の東大医学部講師を有する叡学会(株)合格の天使が全国の受験生にお贈りする確固たる受験結果と検証に基づいた医学部受験生のための生物勉強法と対策です。是非役立てて医学部生物を攻略してください!
医学部、難関理系受験生向けの生物勉強法コンテンツ
医学部、難関理系受験生向けの生物勉強法コンテンツでは以下の項目を掲載しています。
1.医学部受験=生物選択ではない
2.生物受験は医学部入学後有利?
3.医学部受験生の科目変更の例
4.医学部受験生が誤解している生物の入試問題の捉え方
5.生物の医学部入試問題の難しさには2種類ある
6.受験生物の性質
7.生物勉強法の全体像
8.生物の基礎習得段階の勉強法
9.生物の基礎をマスターする問題集・参考書
10.標準レベル段階の生物勉強法
11.知識習得及び生物の記述・論述対策の問題集・参考書
12.応用レベル段階の生物勉強法
13.考察論述対策の問題集・参考書
13.東大医学部/理三合格者の生物勉強法
14.共通テスト生物の勉強法
理系受験生のための共通テスト生物の勉強法
理系受験生のための共通テスト生物の勉強法
このコンテンツで説明してきた生物の勉強法をもとにきっちりと生物の基礎力をつけていき、 二次試験対策・私大対策を行えば、8割~9割程度の得点を獲得できる知識と思考は十分身につきます。
しかし、共通テスト生物の出題特性に合わせた問題慣れや対策がおろそかであれば 共通テスト本番で高得点、満点を獲得できません。
生物の共通テストで9割超、満点を獲得するために以下のコンテンツも是非ご覧ください。